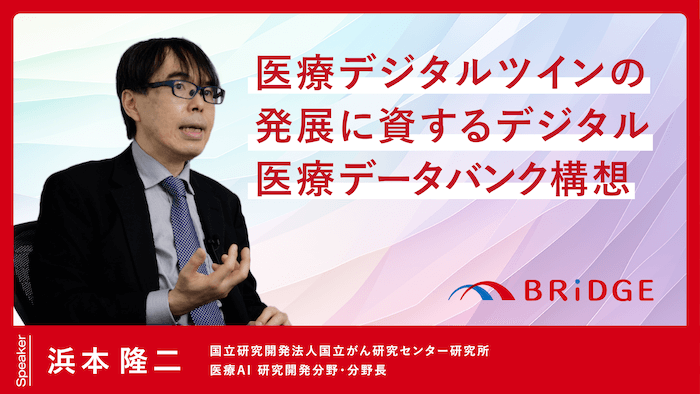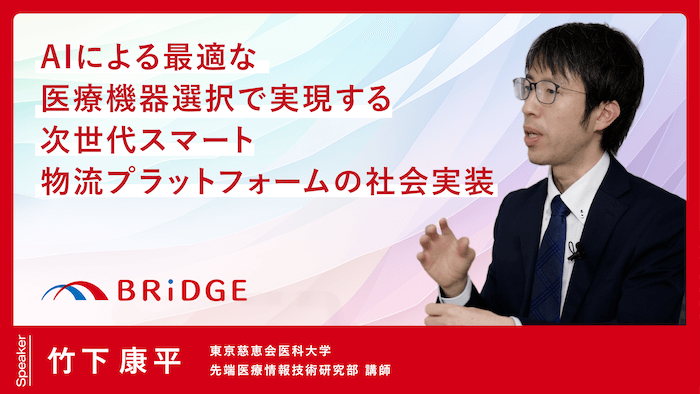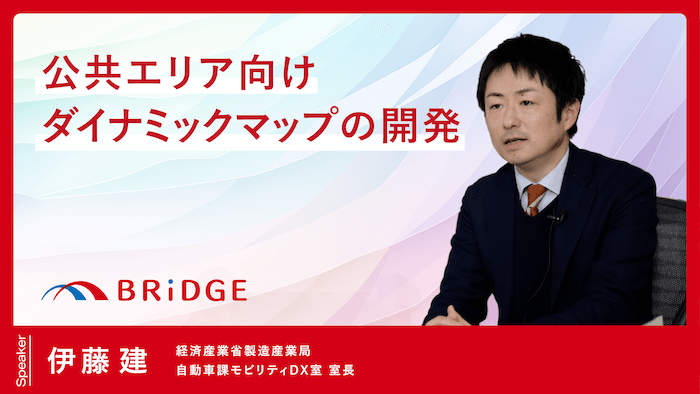施策テーマ 生物多様性と農業生産を脅かす侵略的外来種の根絶技術の開発
プログラム推進者
※ 肩書き・所属は取材当時

森 幸子
農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究開発官(基礎・基盤、環境)室 研究開発官
経歴
1995年農林水産省入省、同省農林水産技術会議事務局バイオテクノロジー課、生産局技術普及課、内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付参事官、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室長等を経て、2023年より現職。
経歴
1995年農林水産省入省、同省農林水産技術会議事務局バイオテクノロジー課、生産局技術普及課、内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付参事官、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室長等を経て、2023年より現職。

松本 英昭
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 室長
経歴
1997年環境庁(現 環境省)入庁。環境本省や地方事務所での勤務の他、在ブラジル日本国大使館、宮内庁出向、関東地方環境事務所国立公園課長・自然環境整備課長、生物多様性センター長等を経て、2023年9月より現職。
経歴
1997年環境庁(現 環境省)入庁。環境本省や地方事務所での勤務の他、在ブラジル日本国大使館、宮内庁出向、関東地方環境事務所国立公園課長・自然環境整備課長、生物多様性センター長等を経て、2023年9月より現職。

大久保 悟
農研機構 農業環境研究部門 農業生態系管理研究領域長
経歴
1998年東京大学大学院博士課程修了。博士(農学)。科学技術振興事業団科学技術特別研究員、東京大学大学院農学生命科学研究科助手/助教、農業環境技術研究所主任研究員を経て現職。
日本をはじめインドネシアなどモンスーンアジアの農業景観における生物多様性と生態系サービスの評価の研究に従事。
経歴
1998年東京大学大学院博士課程修了。博士(農学)。科学技術振興事業団科学技術特別研究員、東京大学大学院農学生命科学研究科助手/助教、農業環境技術研究所主任研究員を経て現職。
日本をはじめインドネシアなどモンスーンアジアの農業景観における生物多様性と生態系サービスの評価の研究に従事。

五箇 公一
国立環境研究所 生物多様性領域 生態リスク評価・対策研究室 室長
経歴
1990年、京都大学大学院修士課程修了。同年宇部興産株式会社入社。1996年、博士号取得。 同年 12月から国立環境研究所に転じ、 現在は侵入生物研究チーム・リーダー。
専門は保全生態学、農薬科学、ダニ学。外来生物防除、農薬リスク管理、および人獣共通感染症対策など、様々な生態リスク研究を通じて、生物多様性と人間社会の関わり方および持続性について模索している。
経歴
1990年、京都大学大学院修士課程修了。同年宇部興産株式会社入社。1996年、博士号取得。 同年 12月から国立環境研究所に転じ、 現在は侵入生物研究チーム・リーダー。
専門は保全生態学、農薬科学、ダニ学。外来生物防除、農薬リスク管理、および人獣共通感染症対策など、様々な生態リスク研究を通じて、生物多様性と人間社会の関わり方および持続性について模索している。
施策について

目指す社会の姿:様々な技術を用いて侵略的外来種に即時に対応し、防除可能な社会
侵略的外来種とは、人間の活動によって他地域から持ち込まれ、生態系や農業に深刻な影響を及ぼす生物を指します。近年、日本における侵略的外来種のうち、植物のナガエツルノゲイトウが問題視されており、農地や水路で繁茂し、農作物の収量減少や希少植物の生育環境悪化を引き起こしています。この植物は再生力が非常に強く、刈り取りなどの物理的な駆除では断片化した茎や根から再生するため、水路や河川などの水系全体で対応することが必要です。
そこで本BRIDGE施策では、より広範囲を省力的に探索する技術や薬剤の環境影響評価の技術開発に取り組むことで、侵略的外来種に対して迅速かつ効果的に対応できる社会の実現を目指しています。


私たちのミッション
効果的な防除と自然環境保全のために、外来種探索技術の省力化や薬剤防除の生態リスク評価を行い、その成果をもとにした水系全体での防除体系の確立に取り組みます。
キーワード:ドローンによる探索・防除技術
侵略的外来種への対策では、侵入初期に対象となる植物を発見し対処することが重要であるため、現在ドローンを活用した画像解析技術が注目されています。発生初期の小さな個体を見つけるためには低空飛行で詳細な画像を撮影する必要がありますが、広域的なモニタリングを行うには高空飛行が適しており、詳細な探索と広範囲の探索の間にトレードオフが存在しています。この課題を解決するため、群落(同じ場所に生育する植物の集団)を検知できる技術を開発中です。群落であれば高度を3倍に上げても検知可能で、かつ探索範囲を10倍以上に広げられることが分かり、詳細探索と広域モニタリングを組み合わせた効果的な技術として開発を進めています。
また、ドローンを用いたスポット防除技術では、環境負荷の少ない化学薬剤の処理方法を開発中です。薬剤散布時のドリフト(意図しない場所への飛散)を防ぐため、点滴処理という方法を採用しました。さらに、水滴が植物表面ではじかれないようにするために、展着剤を加えて薬剤が植物に浸透しやすくなる工夫を行うことで、除草剤の効果が向上することが確認されました。今後も現地実証を重ね、低環境負荷で効果的な防除技術の実用化を目指しています。
本課題の直近の成果・ユースケース
上述のドローンなどを用いて化学薬剤を散布することで効率的な防除が可能となりますが、化学薬剤は生態系への環境負荷が明らかでないため、農地外における使用が認められていません。
この課題を解決するために、除草剤の使用基準や影響を調査するスクリーニングシステムを構築しました。成長量や光合成量を測定することで植物種ごとの薬剤感受性を把握し、環境中での安全な使用基準を設定する基礎データを収集しています。
さらに、河川や陸地を模した「メソコズム」と呼ばれる実験生態系を構築し、除草剤の影響を実際の環境に近い条件で評価する試験を開始しました。模擬河川での実験データをモデルに反映させることで、より精度の高いリスク評価を進めています。これらの成果を基に、外来種防除における安心・安全なガイドラインの策定を目指しています。
読者へのメッセージ
薬剤防除は非常に有効な手法ではありますが、心配される点も少なくありません。私たちは、安心・安全で確実な防除方法を皆さまにご活用いただけるよう、基礎的なデータをしっかり蓄積し、その成果をお示ししていきたいと考えています。この研究事業にぜひご注目いただければ幸いです。
記事作成時期2025年3月11日
(記事の内容は作成時時点のものです)
内閣府の
科学技術・イノベーション
に関する取り組み
科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。